2019.4.24
- みずこしふみ
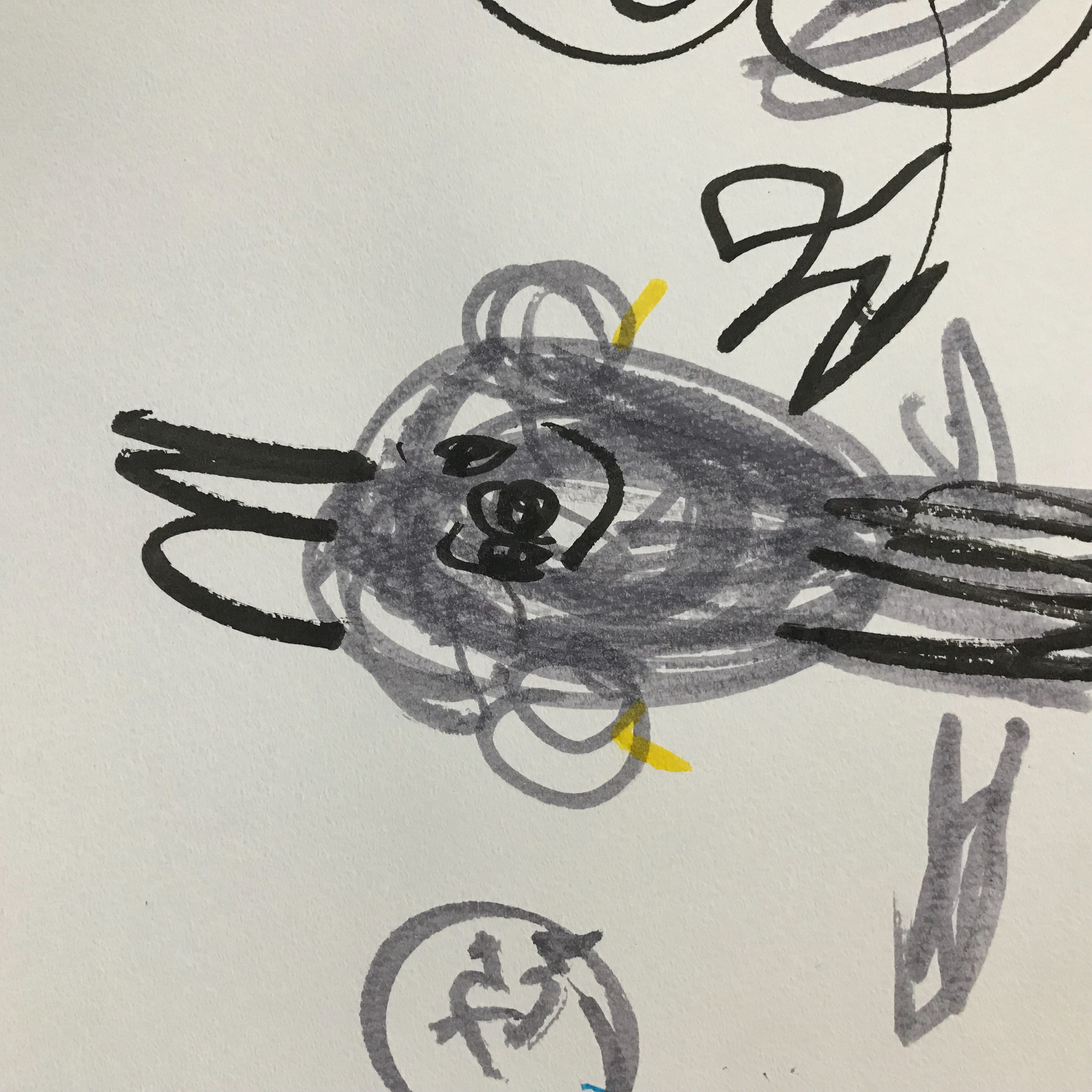
- 2019年4月23日
- 読了時間: 3分
道具を使う
ということは
動物学的に言うと
ひとつの知能のガイドライン
となるもので
ヒトだけが持ってることでは
ないのだけど
道具があることで
ヒトは随分と生活が変わっていった
書くという行為の先に
書き残せる道具が作られ
それによって
言葉の伝達以外の
目の前にいる人以外の
正確な情報の伝達ができるようになり
それによって
ひとりの人生では
到達し得なかった
膨大な量の計算式や摂理や物理を取り込んで
1人の人間で
たくさんの先人の力を借りて
生きることができるようになった
そうして生活が変わっていった
道具は
使い方で
色んな広がりがあって
道具で できること がある反面
道具が邪魔をする こともある
道具のせいっていうと
それもまたちょっと違うのだけど
その場にその道具は違ったとか
その子にその道具は違った
っていうことは
たくさんあって
あなたにはこれよ!
と正解がすぐみえるものでもなくて
やってみて
なにかひっかかる状況があれば
道具も理由のひとつにあげていいはずで
うまく切れない
うまく貼れない
うまく塗れない
この うまく っていうのは
上手にっていうんじゃなくて
思ったようにっていう意味なんだけども
ハサミが手にあってるのか
本当に使いたい方の手でもってるのか
のりは指でつけるのなら
適量が取りやすい容器なのか
適量がわかるのか必要なのか
手を拭くものはあるのか
筆は持つところが長すぎないか
ころころ転がっていかないか
見るべきところはたくさんあって
ほっといてもやる子は
自分でやりやすい環境を少しずつ考えて
整えていけるけど
みんなでやるときや
造形遊びを使って、その子の力を
のばしていきたい
と思った時は
道具は本当に大切
やらないのは
道具や環境が
やれなくさせてると考えて
ひとつひとつ
クリアにしていきたいと思う
今年から大人へのアプローチに
力を入れはじめて
保育士さんに道具や環境の配慮を
少しずつ伝えはじめてて
すぐに動いてくれる、
考えてくれる保育士さんばかりで
とてもいい環境でスタートできてる
まだまだ私も手探りで見つけきれてない
道具もあるのだけど
まずこどもたち
そしてクラス、保育園に合わせて
できる限りの
道具、環境を整えて
もっともっと
こどもたちの力を引き出したいと思う
いい道具ばかりがいいわけではなくて
もう捨てられるのを待つだけ
の道具も大切
絵の具遊びはじめての年少さんや年中さん
筆を大事に使ってね
より、
絵の具遊びを楽しむことが大事。
それから
筆を大事に使おうねと
少しずつ少しずつ伝えて
使いこなせてきたときに
本当に大事に使うべき筆を
渡したらいいのだと思う
道具は最後まで
使える
居場所を変えながら




コメント